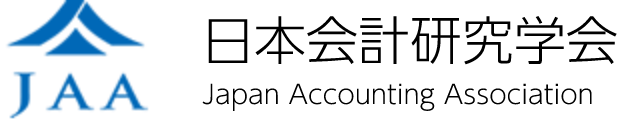日本会計研究学会会則
制定
1937(昭和12)年12月24日
改正
1953(昭和28)年5月29日、1963(昭和38)年4月1日、1969(昭和44)年5月17日、1984(昭和59)年5月24日、1996(平成8)年9月13日、2001(平成13)年9月20日、2002(平成14)年9月11日、2006(平成18)年9月6日、2007(平成19)年9月1日、2008(平成20)年9月8日、2012(平成24)年8月30日、2016(平成28)年9月12日、2021(令和3)年9月8日、2022(令和4)年8月26日、2023(令和5)年9月1日、2024(令和6)年8月26日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
第一条 本会は、日本会計研究学会と称する。
(目的)
第二条 本会は、会計学の研究およびその普及のため、会計学の研究にたずさわる者の連絡および懇親をはかることを目的とする。
(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 毎年1回の大会および毎年1回以上の部会における会員の研究発表および討議。
なお、この事業を行うため、プログラム委員会をおく。
二 日本会計研究学会会報、機関誌『会計プログレス』および機関誌『會計』その他会計学の研究に関する刊行物の発行。なお、この事業を行うため、機関誌『会計プログレス』編集委員会および機関誌『會計』編集委員会をおく。
三 会計用語の統一その他会計学研究に関する委員会の設置。
四 会計学に関する問題についての意見の発表。
五 会計学に関する研究業績の表彰。
六 本会以外の会計に関する学会、機関、および団体等との連絡と共同しての活動。なお、この事業を行うため、以下をおく。
イ 国際交流委員会
ロ 次世代会計研究教育会議
七 その他本会の目的を達成するため適当と認められる事業。
(会員)
第四条 評議員会は、会計学の研究にたずさわる者を別に定める基準に従って、会員として入会することを認めることができる。
(会員の倫理)
第四条の二
1 会員(準会員、院生会員および名誉会員を含む。本条第2項において同じ。)は、別に定める研究倫理施行細則を遵守しなければならない。
2 会員の不正行為は、別に定める規則に従って、調査および審議に付される。
(入会)
第五条 本会に入会を希望する者は、会員2名の推薦をえて、毎年4月末日までに会長(本会の連絡事務所宛)に申込まなければならない。
2 会長は、入会の申込について、別に定める基準に従って、理事会で審議し、その審議結果を評議員会に諮り、承認を求めるものとする。
(準会員の特則)
第五条の二 準会員として入会を希望する者は、会員2名の推薦をえて、毎年4月末日までに会長(本会の連絡事務所宛)に申込まなければならない。
2 会長は、入会の申込について、別に定める基準に従って、理事会で審議し、その審議結果を評議員会に諮り、承認を求めるものとする。
(院生会員の特則)
第五条の三 大学院の博士課程後期課程の在籍者またはこれに準ずる者で、特に 院生会員として入会を希望する者は、会員1名の推薦をえて、毎年4月末日までに会長(本会の連絡事務所宛)に申込まなければならない。
2 会長は、入会の申込について、別に定める基準に従って、理事会で審議し、その審議結果を評議員会に諮り、承認を求めるものとする。
(院生会員から会員への異動)
第五条の四 院生会員から会員への異動に際しては、第五条の手続きに改めて従わなければならない。
(院生会員から準会員への異動)
第五条の五 院生会員から準会員への異動に際しては、第五条の二の手続きに改めて従わなければならない。
(準会員から会員への異動)
第五条の六 準会員から会員への異動に際しては、第五条の手続きに改めて従わなければならない。
(準会員から院生会員への異動)
第五条の七 準会員から院生会員への異動に際しては、第五条の三の手続きに改めて従わなければならない。
(賛助会員の特則)
第五条の八 法人、機関または団体等で、特に賛助会員として入会を希望する者は、会長または理事1名の推薦をえて、毎年4月末日までに会長(本会の連絡事務所宛)に申込まなければならない。
2 会長は、入会の申込について、別に定める基準に従って、理事会で審議し、その審議結果を評議員会に諮り、承認を求めるものとする。
(会費の納入義務)
第六条 会員(準会員、院生会員および賛助会員を含む、以下第六条から第八条までにおいて同じ)は会費を納入しなければならない。
2 会費を納入する義務の成立は会計年度開始の日とし、その納入義務の履行は会計年度開始の月とする。
3 会費の金額は、会員総会が決定するものとする。
4 第五条の三(院生会員の特則)の適用を受ける者の会費は、前項で定める会費の半額とする。
5 海外に在住する外国籍をもつ会員の会費については、前項の規定を準用する。
6 当該会計年度の初めに満65歳以上であり、10年以上本会の会員の経歴を有し、かつ、常勤の職に就いていない場合に、本人が前会計年度中10月末までに本会連絡事務所に申請し、理事会において承認された会員の会費については、第4項の規定を準用する。
(会費の納入方法)
第六条の二
1 会費の納入は、原則として、本会のウェブサイトの会員専用サイトにおけるクレジットカード決済の方法によるものとする。
2 クレジットカード決済に同意しない会員については、本会の所定の銀行口座または郵便振替口座に払い込むものとする。
(退会)
第七条 退会を希望する者は、書面をもって、毎年3月末日までに会長(本会の連絡事務所宛)に申出るものとする。申し出のあった場合は、別に定める基準に従って会員の退会を認める。
2 会長は、会員が長期にわたり会費を滞納した場合などには、別に定める基準に従って、会員を退会させる。
(懲戒)
第八条
1 会員または名誉会員が不正行為その他本会の体面を汚す行為をしたときは、理事会で審議し、その審議結果を評議員会に諮り、評議員会が当該会員または当該名誉会員の懲戒を決定する。
2 前項の懲戒は、会員資格の取消し(除名)、一定期間の会員資格の停止、または厳重注意とする。
(役員)
第九条 本会に次の役員をおく。
一 会長 1名
二 理事 16名以内
三 評議員 70名以内
四 幹事 15名以内
五 監事 2名
(役員の任期)
第九条の二 役員の任期は3年とする。
2 会長は、連続して2期就任することはできない。
3 会長は、任期終了後ひきつづいて自動的に理事に1期就任する。
4 理事は、連続して3期就任することはできない。
5 監事は、連続して3期就任することはできない。
(会長)
第十条 会長は、会員中より互選する。
2 会長は、本会を代表し会務を総理する。
3 会長は、評議員会および理事会を招集し、その議長となる。
4 会長の選挙方法は、別に定める役員選挙施行細則による。
5 会長に事故あるときは、第十七条第1項三に基づき会長代行が選任されるまでの間、会長の所属する地区の理事のうち1名がその職務を代行する。
(評議員)
第十一条 評議員は、会員中より互選する。
2 評議員は、評議員会を構成し、本会の運営につき審議する。
3 評議員会の決議は、出席した評議員の過半数による。
4 評議員会には、評議員の代理人を出席させることはできない。
5 評議員の選挙方法は、別に定める役員選挙施行細則による。
(理事)
第十二条 前会長を除く理事は、評議員会において、評議員中より互選する。
2 理事は、理事会を構成し、会長を補佐して本会の常務を処理する。
3 理事会の決議は、別に定める規則に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数による。
4 理事会には、理事の代理人を出席させることはできない。
5 理事の選挙方法は、別に定める役員選挙施行細則による。
(幹事)
第十三条 幹事は、会員中より評議員会の承認をえて、会長が委嘱する。
2 幹事は、本会の常務の処理につき理事を補佐する。
(監事)
第十四条 監事は、会員中より評議員会が候補者を選び、会員総会が決定する。
2 監事は、本会の会計を監査して、その意見を会員総会において報告するものとする。
3 第九条第五号に定める監事の員数を欠いた場合に備え、補欠監事1名を決定する。
4 補欠監事は、会員中より評議員会が候補者を選び、会員総会が決定する。
5 補欠監事の任期は3年とし、重任は妨げない。
(名誉会員)
第十五条 評議員会の推薦に基づき、会員総会の決議をもって、本会に名誉会員をおくことができる。
2 名誉会員は、会長経験者を対象とする。
3 第九条の二第3項で定める任期終了時に、第1項の決議の効力が生ずるものとする。ただし、本人が辞退したときは、その限りではない。
4 前項により、本人辞退の意思表示のない時は、会長はその旨を理事会、評議員会および会員総会に報告するものとする。
5 名誉会員は、役員および学会賞審査委員の被選挙権を有しないことを除き、会員と同一の権利を有する。
6 名誉会員は、会費を納入することを要しない。
7 名誉会員は、理事会および評議員会に出席して意見を述べることができる。
(名誉会長)
第十六条 評議員会の推薦に基づき、会員総会の決議をもって、本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は、特に本会に功労のあった者の中から選ぶ。
2 第十五条第2項から第7項までの規定は、名誉会長に準用する。
(役員の欠員と補充)
第十七条 役員に欠員が生じたときは、次の処置をとる。
一 評議員については、その任期中欠員を補充しない。
二 理事については、次回の評議員会までは欠員のままとし、直後の評議員会において補充する。ただし欠員が理事の選出区分ごとに1名の場合に限り、直近の改選時における次点者をもって補充する。
三 会長については、直ちに理事の互選により会長代行をおき、次回の大会期間中に会長を選出する。
四 監事については、補欠監事をもって補充する。
2 理事、会長または監事が任期中に交替したときは、前任者の残任期間をもってその任期とし、理事および監事についてはこの期間を1期と数え、会長についてはこの期間を1期と数えないものとする。
(役員の任期満了時期)
第十八条 役員の任期は、第三条第一号に規定する大会終了の時に終了するものとする。
第十八条の二 第六条第5項に該当する会員は学会賞審査委員の被選挙権を有さず、第六条第6項に該当する会員は役員および学会賞審査委員の被選挙権を有しない。
2.準会員となった者、院生会員および賛助会員は、役員および学会賞審査委員の選挙権および被選挙権を有しない。
3. 第六条第5項に該当する会員は、役員選挙に関し選挙権ならびに被選挙権を有するが、同条第6項に該当する会員は、選挙権のみ有する。
(会員総会)
第十九条 本会は、毎年1回定時会員総会を開催するものとし、その時期は、第三条第一号に規定する大会のときとする。
2 評議員会が必要と認めたとき、または、会員総数の3分の2以上の請求があったときには、会長は臨時会員総会を開催しなければならない。
3 会長は、会員総会の開催に先だち、その会場、時期および議案などを会員に通知する。
4 会員総会の議長は、会員総会において、その都度これを選出する。
5 会長は、定時会員総会において会務および会計を報告し、次年度予算案の承認を求めなければならない。ただし、会長は会務および会計の報告を理事にさせることができる。
6 会員総会の決議は、出席会員の過半数による。ただし、準会員、院生会員および賛助会員は会員総会に出席できるが、議決権を有さず、それらの者の数は会員総会の定足数および決議要件に含まない。
(会計年度)
第二十条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
(会則の変更)
第二十一条 本会の会則の変更は、評議員会または会員総数の10分の1以上の会員の提案により、会員総会において、出席会員の3分の2以上の賛成をえて行う。
(解散)
第二十二条 本会の解散は、前条に準じて行う。
(附則)
一 この会則は、制定および改正と同時に施行する。
二 この会則の施行の際現に在任する会長は改正後の会則のもとで選任されたものとみなす。
三 前会長を除く理事の構成は、関東側8名以内、関西側7名以内とする。
四 第十五条による名誉会員は、当分の間、会長経験者を対象とする。
五 本会の本部は、当分の間、一橋大学内におき、連絡事務所を、東京都新宿区早稲田鶴巻町518番地 司ビル3階 株式会社国際ビジネス研究センター内におく。