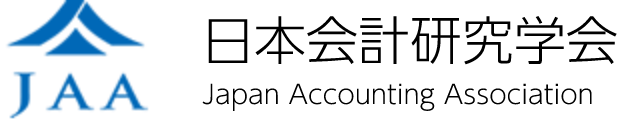レンタルしているWebサーバを用いたホームページ開設に関する内規
理事会承認
2015(平成27)年9月6日
総会改正
2025(令和7)年8月26日
1 (内規の目的)
本内規は、本会がレンタルしているWebサーバ(以下、レンタル・サーバとする)を用いてホームページを開設する場合の基準について定める。
2 (開設できるホームページ)
レンタル・サーバには、本会のホームページとは別に、以下のホームページを開設することができる。
① 大会および部会に関するホームページ
② 特別委員会およびスタディ・グループに関するホームページ
③ その他、ホームページ管理委員会が本会の活動の上で必要であると認めたホームページ
3 (開設の申請)
レンタル・サーバにホームページを開設しようとする者は、以下の事項を明示して、ホームページ管理委員会に開設の申請をしなければならない。
① 開設するホームページの管理者の氏名、所属、メール・アドレス
② ホームページ開設の目的
③ ホームページに掲載する内容
④ ホームページを開設する期間
4 (開設の手続き)
(1) ホームページ管理委員会は、申請された内容を審査し、日本会計研究学会ホームページ管理規程に定める目的に合致していると認めた場合には、ホームページの開設を許可する。なお、その審査にあたって、開設するホームページの内容等について必要な修正を指示することができる。
(2) ホームページ管理委員会は、開設を認めたホームページの管理者に対して、ホームページを開設するためのレンタル・サーバのディレクトリを指定するとともに、レンタル・サーバを利用するためのアカウントと仮パスワードを交付する。なお、ホームページの管理者に付与する権限は、ホームページの開設に関連するものに限定する。
(3) ホームページの管理者は、ホームページ管理委員会の指示に従い、付与されたアカウントおよびパスワードを用いて作成したHTMLデータ等をレンタル・サーバに転送してホームページを開設する。開設したホームページの更新も、ホームページの管理者が行う。
(4) ホームページの管理者は、指定されたディレクトリ以外のディレクトリの内容を変更してはならない。
5 (管理責任)
(1) 開設されたホームページの内容の管理は、それぞれのホームページの管理者が行い、その責任を負う。ホームページのデータのバックアップも、管理者の責任で行う。
(2) ホームページの管理者は、申請した開設期間の終了時点で、ホームページの閉鎖およびレンタル・サーバ上のデータの削除を行うとともに、その旨をホームページ管理委員会に通知する。
(3) 申請した期間終了後もホームページの保存を希望する場合には、その旨をホームページ管理委員会に申請し、管理権限をホームページ管理委員会に移管することができる。この場合、移管後の管理責任はホームページ管理委員会が負う。
6 (遵守事項)
(1) ホームページの管理者は、あらかじめ申請した目的に合致するもの以外の内容をホームページに掲載してはならない。
(2)ホームページを通じた不特定多数に対する個人情報(特定の個人が識別され得る氏名等の情報)の発信は、本会の目的の達成に必要不可欠である場合に限るものとする。また、個人情報を発信にあたっては、必ず本人の同意を得なければならない。さらに、ホームページの管理者は個人の権利や利益が侵害されることがないよう、最大限の措置を講じなければならない。
(3) ホームページの作成にあたっては、原則として自作の画像やデータを用いることとし、無断で他の著作権・知的所有権等を侵害してはならない。研究成果等を掲載するにあたっては、著作権者の同意を得ることとする。
(4) ホームページの管理者は、回答者の同意に基づくアンケート調査等を除き、開設したホームページを通じて無断で閲覧者の個人情報を収集してはならない。
(5) ホームページの管理者は、学会・部会の運営にあたって必要な協賛金・広告料を除き、開設したホームページから収入をえてはならない。
7 (違反への対応)
(1) ホームページ管理者が前項の遵守事項に反した場合、ホームページ管理委員会は当該ホームページの管理者に改善を指示する。
(2) 前号の指示にもかかわらず、当該ホームページの管理者がこれに従わないとき、ホームページ管理委員会は当該ホームページの管理者の同意なく閉鎖することができる。
8 (著作権)
開設されたホームページの著作権は、すべて本会にある。
9 (本内規の改正)
本内規の改廃は、理事会が決定する。
学会は個人情報保護法の対象となるか
個人情報保護法では個人情報取扱い事業者に対して細かい義務規定を課しています。「個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう」となっています。個人情報データベースとは電子的に限らず、紙であっても容易に検索できるように整理された状態のものをいいます。したがって、会員管理をおこなっているような学会はすべからく該当します。これは営利団体・非営利団体、法人・任意団体を問いません。
ただし、これには「政令でさだめるものをのぞく」となっており、政令ではこの基準が個人データが5000件未満の場合となっています。従いまして、会員数が5000人未満の場合は該当しません。しかし、この5000未満という数字は本当の小規模の小売り事業者等を保護するためであり、学会のような社会的責任のある団体では、5000人未満でも個人情報保護法の規定に従うことは必要でしょう。
なお、「大学その他学術団体」を除外するという規定があるので学会は対象外であるという誤解があります。これは会員外への学術目的のアンケートなどを個人情報の保護規定からはずし、学問の自由を担保するためのものであって、会員管理のための個人情報データがこの除外にあてはまるものではありません。新聞社は報道の自由のために個人情報保護法の適用除外を受けていますが、だからといって購読者リストが個人情報保護法の対象とはならないわけではないのと同じです。